こちらの記事はこんな思いをお持ちの方におすすめです。
- 自分の頭でしっかり考えられる子になってほしい。
- 個性や才能を伸ばしてあげたい。
- 学ぶことを楽しんでほしい。
子供の幸せを願っているからこそ、思うことですよね。
生きていくために必要な力は、
学ぶ力です。
なぜなら人間は、生まれたその日からこの力で成長し続けます。
学ぶ力は生きる力の基盤となります。

でも学校が始まるとそれは途端に「足し算ができるかできないか」とか
「漢字が書けるか書けないか」とか「テストで何点とったか」
というものにすり替わってしまうように感じませんか?
学ぶことが、強制された義務のようになっていないか心配になることがあります。
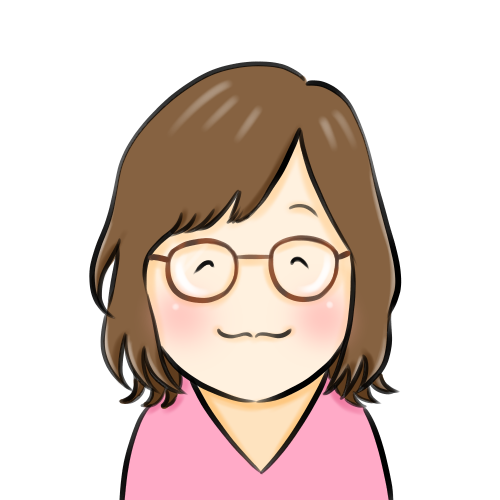
私は小学校の算数のテストで0点をとったその時から、
勉強に苦手意識が生まれ…
嫌いになりました。( 笑)

学ぶ力のベースを作っていくのは家庭です。
乳幼児期を経てきた今だからわかる事でもあります。
乳幼児期のお子さんをお持ちのママたちにとって、参考になればと思います。
幼児期から学ぶ力のベースを作っていくことにはとても意義のあることだと思います。
【ドラえもん】から教わった生きる力
なぜにドラえもん??と思われましたよね。
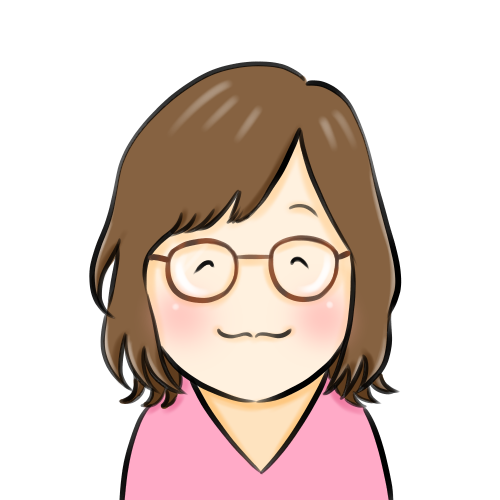
すみません。もう少々お付き合いくださいませ。
私と子供達の大好きな「ドラえもん」
そのストーリー、のび太のキャラクター
ここからたくさんの「生きる力」が学べるのではないかと思ったので
クローズアップしました。
少し前になりますが、「のび太が教えてくれたこと」「のび太という生き方」
こちらの書籍もおすすめです。
ドラえもんのストーリといえば
「のび太が0点をとるたびにママが激怒」→「どらえも〜〜〜ん」
これですよね(笑)
見ている私達はそんなのび太の姿をみて、なんて可愛そうに、、、と思ったでしょうか。
ドラえもんの漫画では、のび太という一見どうしようもない少年にも見える男の子が、
実に魅力的に描かれているように感じます。
なぜでしょう。
多分それは、のび太ならではの個性がきちんと良い面として描かれているからだと思うのです。
✔誰しも生まれ持った個性(特性)がある。
その子のもち味を 「全部それでいい!」と言ってもらえる環境にいられたら、
できる〇>できないXという感覚は生まれなくなる。
家庭においてその環境を用意してあげることができたら
得意じゃないことも、好きになれないことも、丸ごとそれでいいんだ!という思考が自信に繋がる。
そう思いませんか?
生きていくために必要な力ってなんだろう。
常にその本質に目を向けていきたいところです。
「頭が良い」=「勉強ができる」の呪縛
〜チョコぷりんが考えてきたこと〜
- 子供が幸せに生きていけるために、親が出来る事ってなんだろう?
- 学力ってどのくらい必要?
- 学力をつけるために必要な力って何だろ。どんな方法があるだろう。
- 他にどんな力を備わせてあげたら良いのだろう?
- 勉強でつまずいただけで劣等感を持ってほしくない。
- 勉強ができない=駄目な自分 という考え方になってほしくない。
- 自分の力で何度でも立ち上がれる人間になれたら。
- 親として、できる限り多くの選択肢を与えてあげたい。
- 自分が後悔したことを子供には味あわせたくない。
皆さんはどうですか?
初めての子育て、ある本が目に止まりました。
その本にはこんな事が書いてありました。
頭の良さは親にしかつくれない
それまで子供の「教育」について何も考えていなかったので
少しは考えないと、、と焦りを覚えたことを思い出します。
頭が良いとはどういうことなのか、
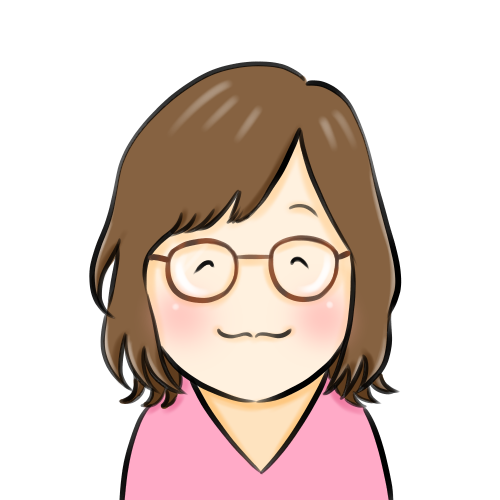
私は、前述の通りお勉強が苦手だったので、、、
頭が良い=勉強ができることだと思っていました。
- 勉強についていけなかったとしても、劣等感は持ってほしくない。
- 勉強は、過程にこそ学びがある。
とにかく、勉強ができないという理由で
学ぶことが嫌にならないように
どうしたらよいかを試行錯誤しました。
- 正解かどうかは、どこまで行ってもはっきりはしない。
- ある程度親が導いてあげることは必要だけど、丁度良くが難しい。
- 子どもが納得しているかどうか、確認しながら勧めたほうがよい。
- 簡単にできること、興味のあることに紐付けた事をさせたほうが生き生きする。
そもそもジャッジを下すのは子ども自身。
どんな状況でも自分にOKが出せて自信の持てる子になれたらいい。
そんな環境を用意してあげられる親になりたい。今はそんな風に思います。
そして常に立ち止まって考えた方が良いこと。
✔自分が安心したいだけで、子供に無理強いしてはないだろうか。
親も学びの最中。
学びながら進みましょう。
実践して良かったこと
とはいえ
実践してきたことの中には無駄ではなかった!と思えることがたくさんあります。
今回はその中のいくつかご紹介します。
その前にひとつだけ注意事項
実践していく中で子供に合わせてカスタマイズは必須です。
最初はここが結構大変に感じてしまったのですが、
その方が上手く回る&早い!
なので、あくまでも一つの事例として参考にしていただければと思います。
- ビジュアルに敏感(美しいもの整ったものが好き)
- 几帳面(整理整頓がしたい)
- 生真面目(期日期限をきっちり守りたい)
- 集中すると周りが見えなくなる(途中でやめられない)
- 競争は好きではない(なにくそ精神はない)
- スキンシップがあれば全てがOK(幼児期は抱っこ派 今もハグ大好き)
- 運動神経は良い方で、よく動き回る
●2歳頃〜入園まで
- 家族で早寝早起き習慣
- やること(食事 あそび 昼寝など、、、)を一緒に考える。
- 1日に5分だけ座って何かする時間を作る。(お絵描き ぬり絵 めいろ パズルなど)
- (3歳頃〜)文字や数などに触れる為のプリントを1日1枚一緒にやってみる。
- 玩具は必要なもの必要な時に。与えるタイミング(ハマっている時期など)を逃さない。
- 外遊びを思う存分させる。とにかく自由に。
●入園から小1くらいまで
- やることリストをひとりで書かせてみる。
- 早寝早起き。
- プリント系 (入学前まで)1日1枚一緒にやる。【朝】
- (小1頃〜)学校の宿題+自分用の学習一緒にやる。【朝】時間で終われるように
- 工作、楽器の演奏、スポーツなど、興味を持ったらできる限り機会をもつ。(無料イベント 体験会などもフル活用)
- 見たまま伝える
- 学習時間は楽しく
- 遊びも学習も時間を決める
一つずつ説明していきます。
「見たままを伝える」
例)取組んだ / 取り組まなかった
丁寧に書いた / 急いで書いた
途中までやった / 最後までやった
肯定も否定もしていない中立な言い方で伝えるということ。
例えば 本人が、「今日はあまりやる気が出なかったけど、頑張った!」と
感じているのならば、その頑張りを認めてあげる。
頑張ったことが良くて、頑張れなかったことが駄目なわけじゃない。
「やる気が出なかったから、今日はやらなかった…」のであれば
疲れていたことを、認めてあげる。話したいことは、それから(笑)
これが親の見守り力が試されるところ。
「学習時間は楽しく」
例)「一緒にやろう」が合言葉。
できた問題をどのように説いたか娘に教えてもらう先生ごっこ。
毎日のプリントはお気に入りのファイルに綴じて気持ちよく並べる。
「時間を決める」
習慣化する。
あくまでも習慣化することが目標なので、内容にはこだわり過ぎない。
例)その日の様子で決める。
好きな問題だけやってみる。
一緒に計算競争をしたり、カードゲームをする。
本人のテンションが上がらないものにいつまでも執着しない。
あくまでも、心がけていたことです。いつもできるわけじゃないです。
- 学習が歯を磨くことと同じくらい当たり前のことになった。
- 学童期の時間管理が楽だった。
- わからない、できない、不得意であることに対して悔しさはあっても劣等感のようなマイナスイメージは感じていない。
中でも、できたかできなかった事だけに目を向けない
これが身についたことは、学習面にとってだけでなく様々場面でメリットがあると思います。
他人と比べるのではなく、常に自分の中でどうだったかを考える。
良悪、〇Xで判断しなくなる。
今の状態をそのまま受け入れて次のステップへ進む。
その繰り返しでよいのだと思えるようになっています。
子供には幸せな人生を歩んでほしい。
子供にとって最善の道を用意してあげたくなってしまうのは当然だと思います。
もしかしたら自分(親)の考えに子供を寄せようとしているかもしれない。
自分(親)が安心できる方法をとろうとしているのかもしれない。
そうやって立ち止まってみる。
その繰り返しが必要だと感じています。
その子が自分の個性を知り、受け入れながら自信を持って進める手伝いをする。
それは
「親だけが用意してあげられる学習環境づくり」なのかもしれません。



コメント