私は娘の高校受験に2年間で約200万円の塾代をかけましたが、結果として確信したのは“お金をかけること”より“関わり方”のほうが大切だということでした。
早くから塾に通わせることよりも、日々の親の関わり方を大切にしたい。
本人の意思で塾へ行きたい!と思った時で十分。
むしろその方が塾を最大限活かせる上に、子どもの自信にも繋が理やすいと実感しています。
これからも家庭の中でもできる「お金をかけすぎない勉強」を実践していきます。
今回は、わが家の経験をもとに小学生向けの無料で学べるおすすめ教材と家庭での工夫をご紹介します。
小学生のうちから学ぶ力を身につけておくことは、その後の学習に必ず役立ちます。
結果、教育費を抑えられることにもつながりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
お金をかけなくても伸びる子の共通点
塾に通っていない子でも成績を伸ばしている子には共通点があります。それは「自分で学ぼうとする力」があること。
この力は、教材よりも環境や声かけによって育つと実感しています。
-
- 失敗を恐れずに挑戦できる
- 勉強を「自分ごと」として考えられる
- 親が「見守り型」でサポートしている
これらは、日々のちょっとした工夫で今すぐ始められます。
家庭でできる!お金をかけない勉強法5選
① 図書館をフル活用する
週末に“家族で図書館の日”をつくったりするのも良いですね。学びを生活の一部にできます。
わが家では、長女が小学校低学年くらいまで「予定がない」「暇だな」「雨だね」という日の定番に図書館がランクインしていました。
息子は、娘が読んでいた絵本があったり幼稚園でも頻繁に借りられたりしたので、ほとんど図書館へは行っていません。小学校へ行く頃には、スポーツ三昧で図書館に興味なしだったので行っていません。
お子さんが興味を示すようであれば、図書館は興味を広げるのにうってつけの場所です。
② 無料プリントサイトや学習アプリを使う
例えば「ちびむすドリル」や「NHK for School」は、楽しみながら学べるコンテンツが豊富です。
小学校では、NHK for Schoolを使った授業もしています。
ちびむすドリルや無限プリントは、本当にお世話になりました。
コピーの手間はありますが、できるだけ費用を抑えたいご家庭にはおすすめです。
学習アプリも豊富ですよね。
我が家では、息子が日本地図パズル ひとコマ漢字 算数忍者あたりをよく使っていました。
③ 日常生活の中で“学び”を見つける
- 買い物のときに合計金額を予想する。
- 料理で分量を計算する。
- 車の速さを体感しながら数字で確認する。
- お菓子の分け方を分割や等分で考える。
- お風呂で浮力を体感する。
しっかり説明するのではなく、話題として話すと良いと思います。
「◯割引ってことは◯%引きってことか。」
「〇〇って長野県さんが多いね。」
「4等分して2つずつ食べたから、結局半分こってことだね!」
なんとなく耳にしているうちに、子どもの方から疑問が飛んでくるようにもなります。
こう考えると毎日が話題の宝庫です。
親子で遊ぶこともおすすめです!
④ 親子で一緒に学ぶ時間を作る
親が教える立場から共に学ぶ姿勢に変えると、子どもは自然と物事に前向きに取り組むことが増えると感じます。
私自身も、子どもの興味があることを一緒にやってみることで学ぶ姿勢が変わりました。
大人の学ぶ姿が当たり前の光景になることは、実は最も子どもの学ぶ姿勢を育てる近道だと思います。
子どもが最初に真似をするのは親ですから。
⑤ 続ける工夫を一緒に考える
上手くいった時もいかなかった時も考える癖をつける
そのためにまずは親が「質問」をして、子どもが考えるきっかけをつくる。
一緒に考えながら、いつしか一人で考えられるようになっていきます。
親の関わり方で「お金をかけない学び」が変わる
私が経験したように、教育費がストレスになると親子関係にも影響します。
例えば、親の否定的でプレッシャーになるような関わり方は、子どもの意欲や自信を失ってしまう可能性があります。どんなに質の良い教材を使っても、先生の教え方が上手でも、価値が半減してしまうのです。
言い換えれば、子どもが自信を持って前向きに取り組んでいけるような関わり方は、お金よりも心強いサポートになります。
だからこそ、「お金をかける」ではなく「関わり方」を大切にしたいと考えるようになりました。
失敗を恐れない声かけを
「バツは失敗じゃない」「できなかったことが次に繋がるチャンス」
そんな声かけが、勉強嫌いの子の自己肯定感を育てます。
失敗は単なる結果。このやり方では上手くいかなかったという結果に過ぎません。
でも、親自身が心からそう思わなければ伝わらないこともあるかもしれません。
少しずつ声かけを心がけていくことで、私自身の「バツ」「できない」への捉え方も変化していきました。
結果よりも過程を認める
結果(点数・勝敗)ではなく、過程(努力・試行錯誤)を言葉で伝える。
「昨日より自分で考えていたね。」
「疲れていたけど、これだけはやろうとしたんだね。」
といった成長に気づける言葉が、子どもの意欲を伸ばします。
どうしても結果の話が多くなりがちですが、意識しながら声かけをしていくだけでも、子どもにはちゃんと伝わっていくと実感しています。


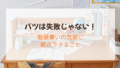
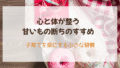
コメント